──デザイナーDavid Tongeが語る、日本工芸の本質とこれから
When Thought Takes Shape: Designer David Tonge on the Essence of Japanese Craft
はじめに – 「もの」ではなく「思考」をかたちにする仕事
工芸は、単なる“ものづくり”ではない。そう語るのは、英国ロンドンを拠点に、日本企業や職人たちと20年以上にわたり協働してきたデザイナー、David Tonge(デヴィッド・トング)氏です。
David氏が惹かれてきたのは、完成された「作品」ではなく、その背後にある「思考」──素材との向き合い方、プロセスの哲学、そして文化に根ざした技術の意味。それらを「かたち」にする、日本の工芸の本質に魅了されてきました。
本記事は、日本の工芸や精神性を多角的に掘り下げていくインタビューシリーズの第1回として、David氏の視点から「侘び寂び」や「不完全さ」「手仕事の哲学」「文化的差異」などを軸に、デザイナーとして見つめる日本工芸の本質とその未来の展望について語っていただいたものです。
Q1 ― 工芸の魅力は「素材」よりも「考え方」にある
Q:日本の工芸といえば、どんな素材や技法を思い浮かべますか?
正直言うと、ひとつに絞るのはとても難しいですね。たしかに、漆や藍染、金箔などはどれも魅力的です。でも僕にとっては、それらの技法自体よりも、それを支えている「考え方」や「プロセス」にこそ惹かれるんです。日本の工芸には、手間を惜しまない姿勢や、細部への徹底した集中力、そして素材と真摯に向き合う思想が込められています。
特定の技法や材料よりも、「なぜこのかたちになったのか」という問いに答えようとする姿勢が面白い。たとえば、金箔も漆も好きですが、僕にとっては“何を使ったか”よりも、“どうしてそれを選び、どう作られたか”がもっと重要なんです。だから「この技法が一番好き」と断言するより、「この思考に惹かれる」と言う方が自分にはしっくりきますね。
Q2 ― 日本と西洋の「自己表現」の違い
Q:日本と西洋のクラフト精神にはどんな違いを感じますか?
大きく違うのは、「自己表現」に対する考え方です。西洋では、学校教育の段階から「自分の意見を持ち、声に出すこと」が重要とされます。アーティストやクラフトマンにとっても、「個性」や「独自性」を前面に出すのが当然のように求められる文化なんです。
一方、日本ではむしろ「空気を読む」「調和を大切にする」といった集団的価値観がベースにあります。だから日本の職人やアーティストは、自分を前面に出すというよりも、技術や完成度に焦点を当てている印象があります。
この違いを象徴するのが、柳宗悦の『The Unknown Craftsman(無名の職人)』という本です。そこでは「日本の職人は作品に自我を出さず、ただひたすら良いものを作ろうとする。その姿勢こそ尊い」と書かれています。そしてそれに共鳴したのが陶芸家の濱田庄司で、彼もまた“無名性”や“無心での制作”を重んじていました。
この本を読んだとき、僕自身もハッとしました。西洋では「自分の声を伝えろ」と言われ、日本では「黙して語らず」の美学がある。その根本的な違いが、クラフトのアプローチにも色濃く反映されていると思います。
Q3 ― 職人はなぜ「売ること」が苦手なのか?
Q:日本の工芸家は、素晴らしい技術を持ちながらも“売ること”が苦手だと言われますが、それについてどう思いますか?
それは日本だけの話ではありません。たとえば、イギリスの陶芸家たちも同じ問題を抱えています。彼らは“器をより軽くする”、“釉薬を改良する”といった技術の探求に夢中ですが、ブランディングやマーケティングにはほとんど関心がありません。ビジネスの話になると、むしろ居心地が悪そうにすることも多いですね。
日本の職人たちも、驚くほど高い技術を持っているのに、それをどのように“外に伝えるか”についての訓練を受けていない場合が多い。だからこそ、第三者がその“語り手”になる必要があると思っています。
デザイナーや編集者にとっての役割のひとつは、作り手の思考を“物語”というかたちに翻訳することです。そうすることで初めて、世界中の人々がその工芸品の本当の価値に気づけるようになるのです。
Q4 ― 海外で伝えるには、“複雑さ”ではなく“深さ”を
Q:日本の工芸を海外に伝える際に、最も大事なことは何だと思いますか?
僕が大事にしているのは、“複雑さ”を説明することではなく、“深さ”を伝えることです。
日本の工芸は、工程が非常に細かく、技術的にも高度です。でも、そのディテールのすべてを逐一説明することが、必ずしも感動を生むわけではありません。
大切なのは、「なぜその工程が必要だったのか」「なぜこの素材を選んだのか」といった背景を伝えることです。たとえば「この器には何十回も漆が塗られている」「この金箔は一万分の一ミリの薄さだ」といった情報も、それが“なぜ必要だったのか”が語られることで、はじめて意味を持つんです。
それが伝わったとき、工芸品は“物”から“物語”に変わり、人の心を動かす力を持つようになるのだと思います。
Q5 ― 色彩の違いが生む“誤解”と“発見”
Q:日本の色彩感覚について、何か感じることはありますか?
日本の色彩は、とても繊細で曖昧さに富んでいます。それが西洋人には、最初は“弱い”とか“控えめ”に感じられることがあるんです。たとえば、パッケージに使われる色がすべてグラデーションだったり、色の変化がとてもやわらかい。
その後、スペイン人著者による日本の色彩に関する本──ロッセッラ・メネガッツォ著の『IRO』──を読みました。その中で、『源氏物語』における「襲の色目(かさねのいろめ)」の意味が解説されていて、目が開かれるような思いがしました。グラデーションは単なる美的選択ではなく、身分や季節、感情などに関わる深い文化的意味を持っていることに気づいたのです。
つまり、グラデーションが美しいのではなく、“グラデーションに意味がある”ということ。それを理解した瞬間、日本の色彩の奥深さが一気に開かれました。このように、色に対する“感性の翻訳”も、日本工芸を伝えるうえで大きな鍵になると感じています。
Q6 ― Wabi-Sabiと「リアルな日本」のあいだにあるもの
Q:外国人が抱く「日本=ミニマルで禅的」というイメージについて、どう思いますか?
正直に言うと、それは一種の幻想だと思っています。もちろん、禅や侘び寂びといった概念は日本文化に存在していますが、それが日本のすべてではない。実際の日本は、もっと雑多で、カラフルで、ノイズに満ちています。
僕が訪れた多くの家庭では、“もったいない精神”によってモノが溢れていましたし、祭りや商店街はとてもエネルギッシュです。京都や金沢のように静謐な美しさを感じる場所もありますが、同時に新宿や渋谷のような“雑多な日本”もまた真実です。
僕は、日本の本当の美しさは、「静けさと混沌」「豊かさと欠如」といった対比や揺らぎの中にあると信じています。日本を正直に描こうとするならば、その両方の側面をきちんと表現する必要があるのです。
Q7 ― 自作における「日本の影響」の受けとめ方
Q:ご自身の作品には、日本の影響があると思いますか?
もちろんあります。でも、僕は“日本の様式をコピーしたくない”と強く思っています。むしろ、“日本の精神”や“考え方”を自分の文脈で再解釈したい。
たとえば僕は今、陶芸に取り組んでいて、金継ぎのように「壊れたものを直すことで美しくなる」という哲学に強く惹かれています。また、「グレージング・ペンシル」という技法を使って、手描きのような線を釉薬で施す試みもしています。
僕が目指しているのは、“日本っぽく見える作品”ではなく、“日本で過ごした経験が自然とにじみ出る作品”。つまり、“Not from Japan(日本そのものではなく)”、“of Japan(日本に由来する)”なものを作りたいんです。
Q8 ― 石川県への思いと、未来のコラボレーション
Q:今後、日本の工芸とどのように関わっていきたいですか?
僕は石川県が大好きなんです。金沢や加賀、能登など、本当に多様で豊かなクラフト文化があります。特に金属加工、金箔、漆、陶芸…そのどれもが本当にユニークで、他の地域にはない魅力があります。
今後は、現地の職人たちと一緒に、新しい形のプロジェクトができたらと願っています。ただし、それは“西洋化する”という意味ではなく、“西洋と日本が対等に会話しながら共に作る”という意味です。
僕は翻訳者であり、橋渡し役でありたい。日本のクラフトを、欧州の暮らしや価値観とつなぐような、新しいかたちの提案ができれば最高ですね。
おわりに ― 工芸は、考えを語る「物語」である
David Tonge氏の語りは、私たちに改めて問いを投げかけてきます。工芸とはいったい何なのか。それは、美しいものを作ることなのか、伝統を守ることなのか、あるいはその両方なのか──。
彼の言葉を通して見えてきたのは、工芸とは「考えをかたちにする行為」であるという視点です。たとえば、一見すると静かで無口に見える日本の器には、実は深い思索と感情が込められている。それは、目立たない方法で語られる「無名の職人の哲学」であり、ひとつの器に塗り重ねられた何十回もの手仕事が、物言わぬ声として語りかけてくる。
そして、David氏が繰り返し語ったように、工芸は“物”として完結するのではなく、そこに宿る“なぜ”を通じて、人と人、文化と文化、時代と時代をつなぐ“物語”になる。つまり、工芸とは伝達の手段であり、想像力を刺激するメディアであり、そして記憶と精神性を未来へと橋渡しする営みでもあるのです。
いま、私たちが日本の工芸を世界に届けようとするときに必要なのは、技術だけではありません。そこにある「思考のプロセス」を正確に、そして詩的に翻訳する“語り手”の存在です。
西洋の人々が本当に知りたいのは、どんな技法が使われているかではなく、「なぜその形になったのか」「なぜいま、この素材を使うのか」といった背景です。David氏自身が「コピーではなく、“of Japan”を目指す」と語ったように、重要なのは“本質”をどう伝え、どう共創していくかにあります。
工芸は、無名の職人の哲学を未来へつなぐ「静かな思想」です。そしてその思想を、世界の異なる文化の中でも響かせるために、私たちには“語る力”と“翻訳する感性”が求められている──David氏の静かで力強い言葉は、そう語りかけてくれているように思えてなりません。
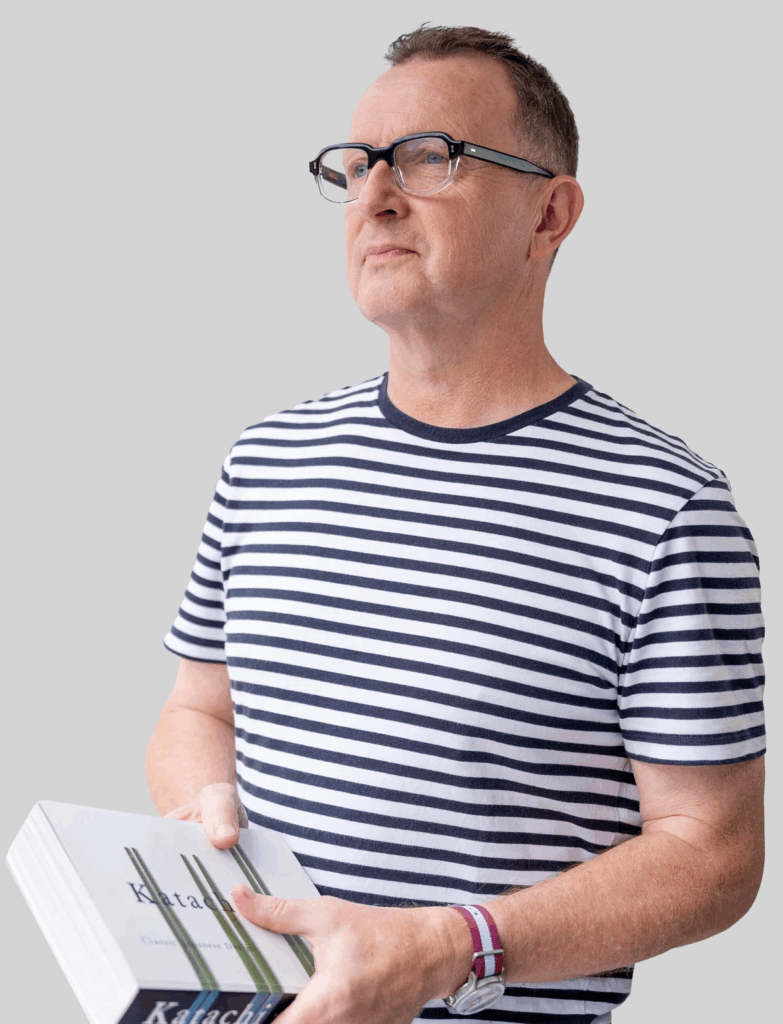
David Tonge(デヴィッド・トング)プロフィール
Founder and Director, The Division(ザ・ディヴィジョン)
David Tonge(デヴィッド・トング)は、ロンドンを拠点とするデザインコンサルタントスタジオ「The Division」の創設者であり、プロダクトデザイン、クラフトを起点としたイノベーション、国際的なコラボレーションを専門とする英国人デザイナーです。
ブラザー、パナソニック、資生堂、象印など、20年以上にわたり数多くの日本企業と協働してきた経験から、日本の素材文化やものづくりの哲学に対する深い理解を培ってきました。
彼の活動はインダストリアルデザインからクラフトリサーチまで幅広く、しばしば西洋と日本の思考様式の橋渡し役としても機能しています。また、自身も熟練の陶芸家であり、日本の影響を単なる模倣ではなく、思慮深い解釈として自身の作品に取り入れています。
文化交流への強い関心を持ち、デザインと工芸が物語性や文化的翻訳の手段として共存できる可能性を、今なお探求し続けています。